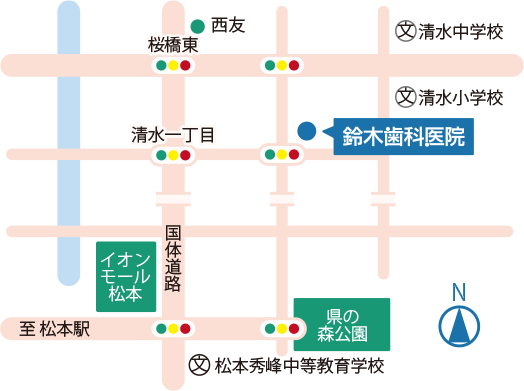こんな症状がありませんか?
- 口を開けようとすると痛い
- 顎ががくがくや、こきこき音がする
- 口が大きく開かない
- 口が閉じづらい
- 急にかみ合わせ・咬む感じが変化した
- 頭痛・首や肩のこり・耳の痛み・耳鳴りなど
- 口をあけると音がする、違和感がある
- 顎がつかれる
- 顎の痛みや違和感がある方
- 耳の前の痛みや違和感がある
- 咬むときに顎が痛い
- 歯ぎしりやくいしばりのある
このような症状がありませんか?
顎が痛い
顎が思い通りに動かない。
顎の周辺がいつも痛い。
口の開閉で痛みがある。

音がする、違和感がある
口の開閉時に音がする。
噛み合わせに違和感がある。
顔にゆがみが出ている。

顎が疲れる
食べ物が噛みにくい。
食事をしていると顎がだるい。
話していると顎が疲れる。

口を開けられない
大きく口を開けられない。
人差し指から薬指までの3本分が入るところまで口が開けられない。

このような症状は
顎関節症の疑いがあります。
顎関節症は、口を開けたり閉じたりする顎の関節や顎を動かす筋肉(咀嚼筋)に異常が起こる疾患です。上記のような「口が開きにくい」、「音がする」、「顎や耳の周辺の痛い」といった症状が現れる病気です。
原因としては顎関節の異常や関節周囲の筋肉に関連している場合が多いです。また、歯の噛みあわせや歯ぎしり、食いしばりなど、生活習慣の中で歯と歯を無意識にかみ合わせるTCHという癖も関係することがあります。
当院での顎関節症の特徴
- 大学病院口腔外科にて幅広く研鑽をつんだ副院長が、顎関節治療を行っております。
- 顎関節治療難治療になる場合は、MRI撮影の治療の必要性もあり、当院副院長は信州大学非常勤勤務であるため、連携しながらの治療が可能です。
顎関節症の原因
顎関節症の原因は、はっきりとしないことも多く、様々な因子が関係しているといわれております。
歯ぎしりや噛みしめ等の習癖、神経系の異常、外傷、精神・心理的因子、咬み合わせの異常、その他の因子です。その中で一般的な原因は日中や睡眠中のくいしばり、歯ぎしりが考えられております。
生活の中で、くいしばりを行っていることを自覚し、くいしばりが顎関節の原因になっていることを理解してもらい、それを止めるように指導していくことが重要となってきます。
睡眠中の歯ぎしりは、意識することが難しいため、関節への負荷を軽減させる目的でマウスピース(スプリント)を就寝中に装着してもらう場合があります。
また日常生活動作でも悪化するとも言われております。
日常生活で知らず知らずのうちに負担をかけていることで悪化します。
注意すべき生活習慣は以下のようなものがあります。
- 噛みしめ癖、歯ぎしりがある。
- 頬杖をつく、体のバランスで偏りがある。
- うつぶせ寝、または横向きに偏って寝ている。
- 噛みあわせが良くない。
- 硬い食事が好き。
- 顎に負担のかかる趣味
(管楽器やバイオリンの演奏、カラオケや声楽、格闘技、ウエートトレーニングなどのスポーツ)
常に上下の歯が触れていることをTCH(tooth contacting habit)といい、現在非常に問題視されています。
1日に上下の歯が触れないと生活できない時間は、たった20分以内と考えられています。
それは、食事・嚥下(ツバを呑む瞬間)・発音の時間です。それ以外の時間は、当たらなくても生活に支障はないと考えられています。
小さい頃に口を開けたままでいることは行儀が悪いと指摘された人は多いと思いますが、口は閉じることは大事ですが、中で歯と歯は接触させてないようにしないと歯に負担がかかります。
顎関節症の主要な症状
1.痛み
口を開けたり閉めたりするときに、顎関節が動くため、顎関節や周囲に痛みがでます。また、顎関節を動かす筋肉に原因があり痛みが出ることも多いため、どこに原因があるのか診断することが必要になります。
- 顎関節の痛み
- 咀嚼筋痛
- 筋・筋膜性疼痛
2.開口障害
口の開ける量は正常であれば、指三本程度入り、だいたい開口量は約40mmとなっております。開口量が40mm以下の場合となってくると、開口障害、顎関節症が考えられます。 クローズドロックという病態があり、以前から顎を動かすと音が出ていたのが、ある日突然、音がなくなり、口が開かなくなることがあります。この場合マニュピレーション治療やリハビリテーション訓練を行うことで開口障害を改善させます。
3.関節雑音
口を開けたり閉めたりしたときにコキコキ音がなっていたり、ひいてはじゃりじゃり音がしている場合があります。関節の中の関節円板がずれることにより、様々な音が生じることがあります。
顎関節症の治療方法
顎関節症学会ガイドラインに準拠しながら行っていきます。
1. 疾患説明と教育
- 顎関節症の自然経過やリスク因子について説明
患者の不安を軽減するため、病態のメカニズムや進行性でないことを伝える。 - 生活指導とセルフケアの方法
硬い食物の過剰な咀嚼や悪習癖の是正の改善などを指導。歯ぎしりやかみしめなどの自覚および習慣改善指導。
2. 理学療法
- マッサージや温熱療法
咀嚼筋のマッサージやホットパックを用いて、血流の増加や痛みの緩和を図る。 - 電気刺激療法とレーザー療法
筋収縮の誘発や鎮痛効果を期待して電気刺激やレーザーを使用。 - 筋伸展訓練(ストレッチ)
筋痛や開口制限の改善を目的としたストレッチング。
3. 薬物療法
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やアセトアミノフェンを使用して、消炎鎮痛効果を狙う。安全性を考慮し、最小量から時間投与で開始。
4. アプライアンス療法
- スタビリゼーションアプライアンス(スプリントやマウスピース治療)
硬性または軟性プラスチック材料で咀嚼筋の緊張を緩和し、顎関節への負担を軽減する装置。夜間使用が推奨される。
5. 運動療法
- 顎関節可動化訓練や徒手的顎関節授動術(マニピュレーション)
開口制限や運動制限のある症例に対して関節の可動域を改善。
6.症状改善がない場合はボツリヌストキシン注射も考慮
- ボツリヌストキシン(ボツリヌス療法いわゆるボトックス)を顎関節に関与する筋肉に注射することで、歯や顎、筋肉への負担を減らすことで症状の改善を図ります。
顎関節症の治療法は、患者の症状や病態に応じて適切に組み合わせて進められます。また、治療経過や期待される結果について患者に丁寧に説明し、納得してもらうことが大切です。
顎関節症の治療の流れ
問診
症状の経緯、顎関節に影響を与える生活習慣に関して詳しく問診します。
検査
顎関節周囲の筋肉の状態、口の開け閉めの状態、噛み合わせを調べます。
画像検査
パノラマレントゲンにて、顎関節部分の骨の形態や状態や、開閉口時の顎の運動について調べます。CTにて顎関節の形態など精密検査行います。